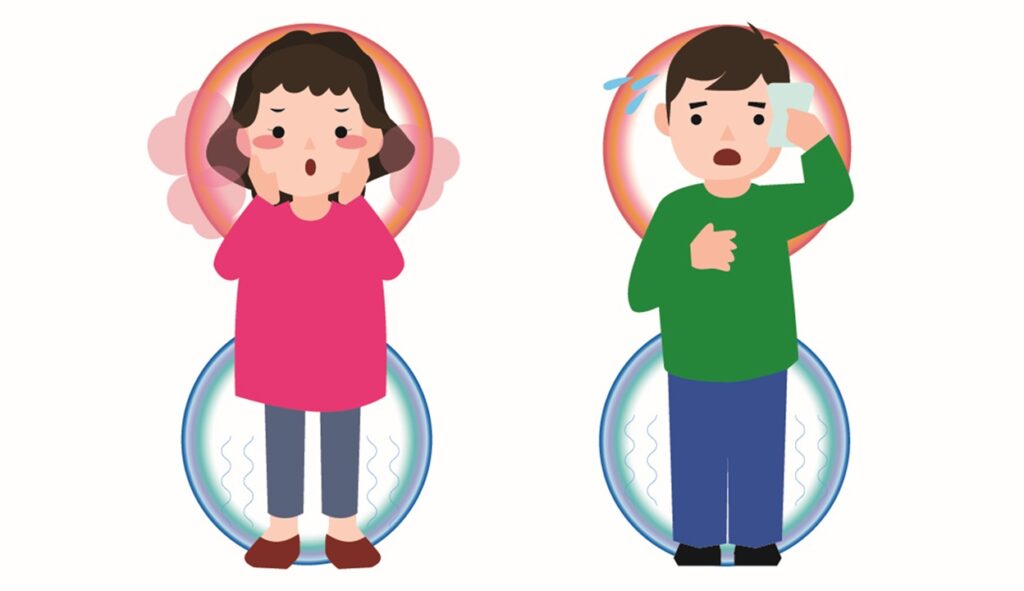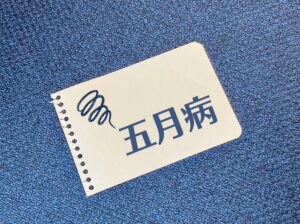
『5月病は、肝の弱りが原因かも』
4月から新しい仕事、生活環境になった方は、そろそろ慣れきた頃でしょうか?
世間一般に言う5月病の症状は、ゴールデンウィーク(以下:GW)明けくらいから出てきます。
症状の例
🔹やる気がでない
🔹眠れない
🔹朝が起きれなくなった
🔹疲れやすくなった
🔹情緒が不安定(気分が落ち込む、またはイライラ)
🔹仕事、学校に行きたくない
そこで、5月病にならないために、漢方視点での原因と解決策をご紹介します。
<原因>
環境の変化に対して心と体が対応できない状態が長期に続くと、肝という臓が影響を受けます。肝は、”伸び伸び”を好むという特徴がありますが、環境の変化で精神的ストレス、物理的ストレスで肝が抑えられると弱ります。肝は、疏泄(そせつ:自律神経のようなもの)を担うので、肝が弱ると乱れます。
肝が弱ったときの典型的な負のスパイラル例を以下に示します。
①肝が弱り、疏泄(そせつ:自律神経のようなもの)乱れる
②脾が弱り(胃腸機能低下)、食欲不振。栄養不足が生じる
③気血(エネルギー、血)が産生力が低下し、肝を含む五臓を滋養できなくなる
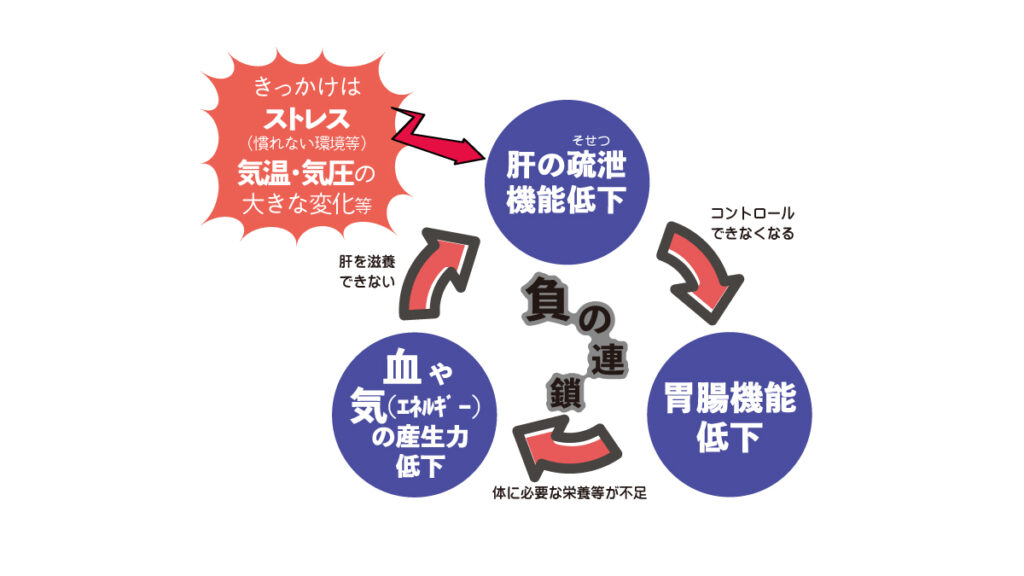
<漢方での解決策>
漢方で5月病にどのように対応していくかというと
養生 7割
漢方薬 3割
のバランスで改善を試みます。
とにかく生活の乱れからの影響が大きいので、なにより養生(生活の改善)が最優先です。
<養生>
🔶3度の食事をとる
特に朝食は抜かない。朝食を菓子パン、栄養ドリンク、栄養ゼリーなどに頼らない
🔶食事はバランスよく食べる
🔶ジュース、お菓子などの甘い物を極力控える
🔶冷たい飲食物は極力さける
🔶十分な睡眠
🔶ストレスを解消
趣味、スポーツ、お友だちとおしゃべりなど、自分の時間を作って、ストレスを解消しましょう。
ただし、睡眠を削るのはNGですよ(^^)
次に回復を早めるために漢方薬をご紹介します。
<漢方薬>
◆食欲不振
イスクラ 健胃顆粒(けんいかりゅう)
香砂六君子湯(こうしゃりっくんしとう)
救心感應丸 氣(きゅうしんかんのうがんき
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
◆疲れやすい
イスクラ 麦味参顆粒(ばくみさんかりゅう)
能活精(のうかっせい)
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
◆イライラ、腹部膨満感
逍遙顆粒(しょうようかりゅう)
柴胡疎肝湯(さいこそかんとう)
四逆散(しぎゃくさん)
◆不眠
イスクラ 温胆湯(うんたんとう)
イスクラ 心脾顆粒(しんぴかりゅう)
柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)
黄連解毒湯(おうれんげどくとう)
「心身一如」と言って、心と身体は表裏一体で影響し合います。5月病のほとんどは、生活の乱れから身体(最初に肝)が弱り。その弱りが心の病(情緒不安定、やる気がでない)を誘引します。よって、漢方では、養生と漢方薬で体を回復させることで、心の病の回復に良い影響を及ぼします。
本ページが、5月病の回復に役立てていただけたら幸いです。
<注意>
本ページで掲載している漢方薬は一例です。
個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。
漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。
熊本 菊陽町 菜の花漢方堂