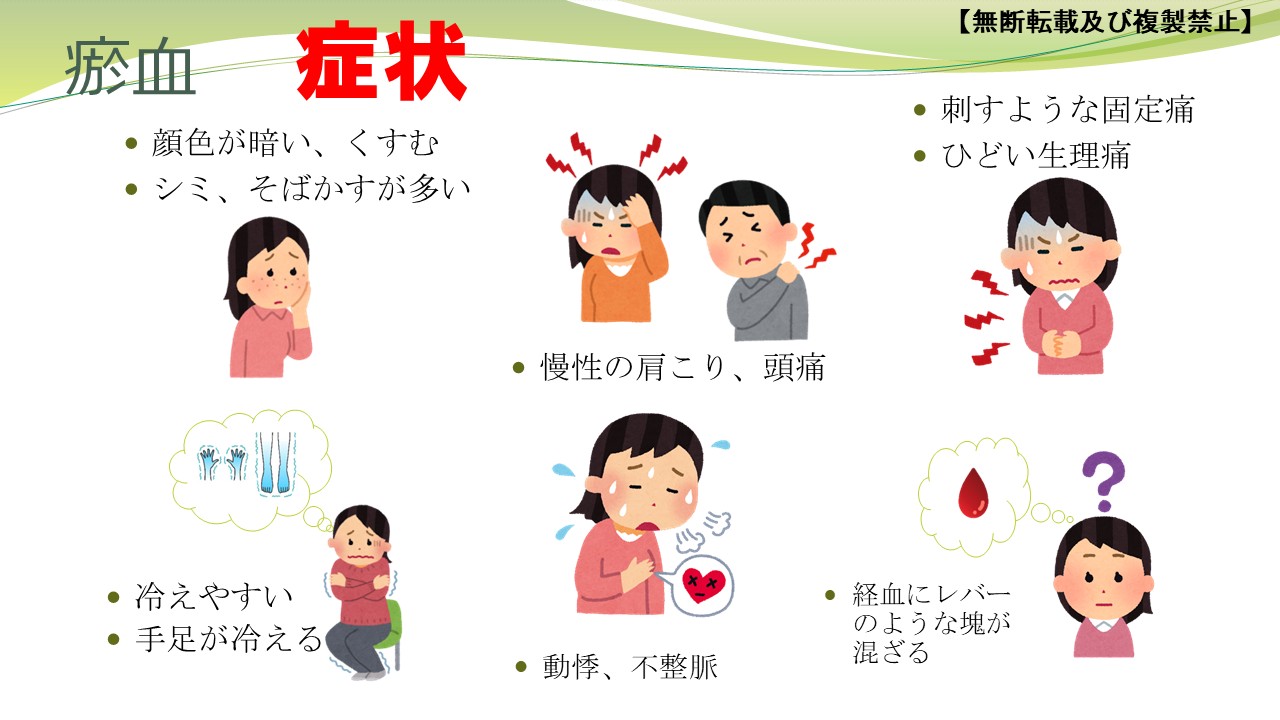『体質別養生法 第7回 ~痰湿~』
7回にかけて紹介してきた体質別養生。今回が最終回です。
取り挙げる体質は、『痰湿(たんしつ)』です。
気血水の水が滞ると痰湿(たんしつ)という状態になっていきます。
イメージするとしたら、ネバネバの水の流れです。
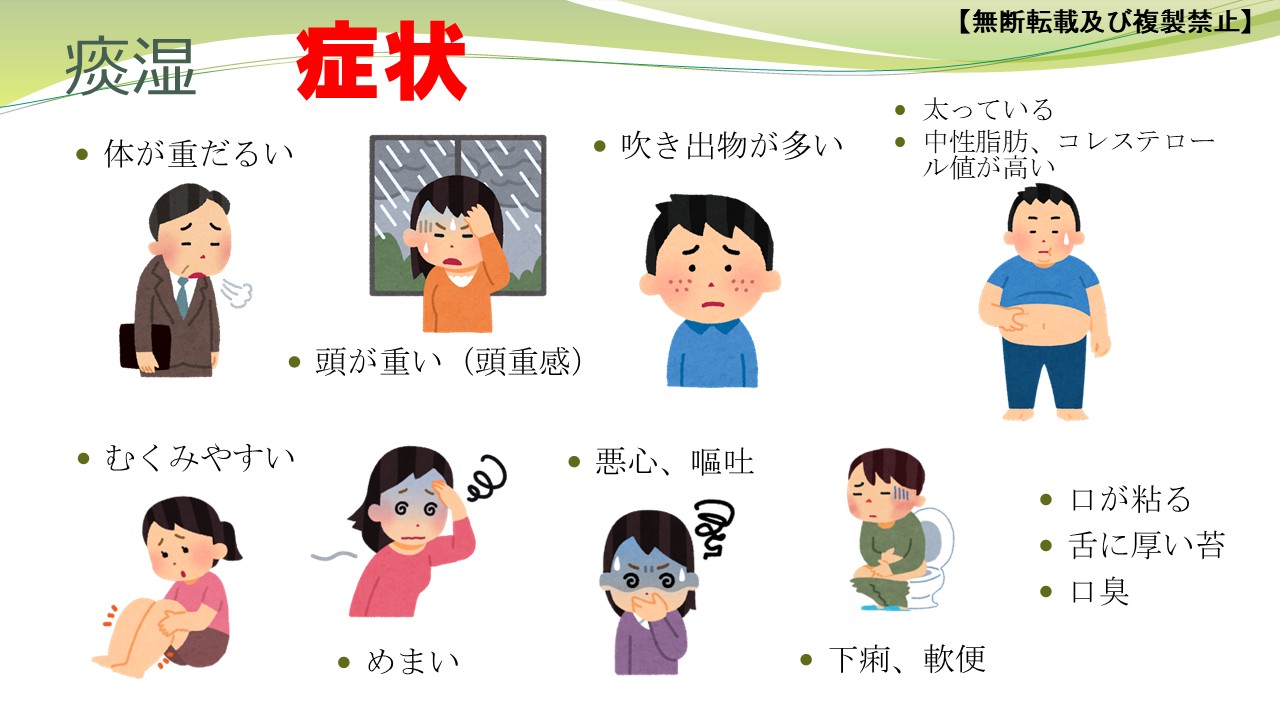
痰湿でよく起こる不調としては
🔹体が重だるい、頭が重い(頭重感)
🔹吹き出物が多い
🔹太りやすい
🔹中性脂肪、コレステロール値が高い
🔹むくみやすい
🔹めまい
🔹悪心、嘔吐
🔹下痢、軟便
🔹排尿痛、残尿感
🔹関節の痛み
🔹口が粘る、舌に厚い苔
🔹口臭
などです。また、怪病多痰(かいびょうたたん)と言う言葉があります。”原因不明の症状は、痰湿(たんしつ)が絡む”ということ表した四字熟語です。
では、痰湿症状を立て直すための養生と漢方薬をご紹介していきます。
瘀血(おけつ)同様、痰湿という体質は、養生を徹底しながら、漢方薬の助けをかりると改善が早まります。養生もほぼ瘀血と一緒です。
<養生>
🔶肥甘厚味、アルコール控える
🔶冷たい飲食物、なま物を控える
特に甘い冷たい飲み物は避ける
🔶冷たい飲み物と一緒に食事をとらない
🔶湿気の多い場所を避ける
🔶夜食、間食を控える
🔶よく噛んで食べる
🔶適度な運動(少し息があがる程度)
🔶オススメ食材
白菜、大根、人参、カブ、緑豆もやし、ごぼう、里芋、タケノコ、こんにゃく
海藻類(わかめ、ひじき、昆布、のり)
きのこ類(しいたけ、えのき、なめこ)
次に痰湿体質で使う漢方薬の一例をご紹介します。
<漢方薬>
◆体が重だるい
勝湿顆粒(しょうしつかりゅう)
藿香正気散(かっこうしょうきさん)
◆めまい、めまいからくる吐き気
五苓散(ごれいさん)
柴苓湯(さいれいとう)
沢瀉湯(たくしゃとう)
◆胃部不快感、悪心、嘔吐
二陳湯(にちんとう)
健胃顆粒(けんいかりゅう)
◆下痢、軟便
健脾散エキス顆粒(けんぴさんえきすかりゅう)
◆排尿痛、残尿感
瀉火利湿顆粒(しゃかりしつかりゅう)
竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)
◆関節痛
清湿化痰湯(せいしつけたんとう)
疎経活血湯(そけいかっけつとう)
五積散(ごしゃくさん)
瘀血(おけつ)と同様に痰湿も、放って置くと重大な病気へとつながります。養生と漢方薬で早めに痰湿を改善し、未病先防で健康を維持しましょう!!
<注意>
本ページで掲載している漢方薬は一例です。
個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。
漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。
熊本 菊陽町 菜の花漢方堂