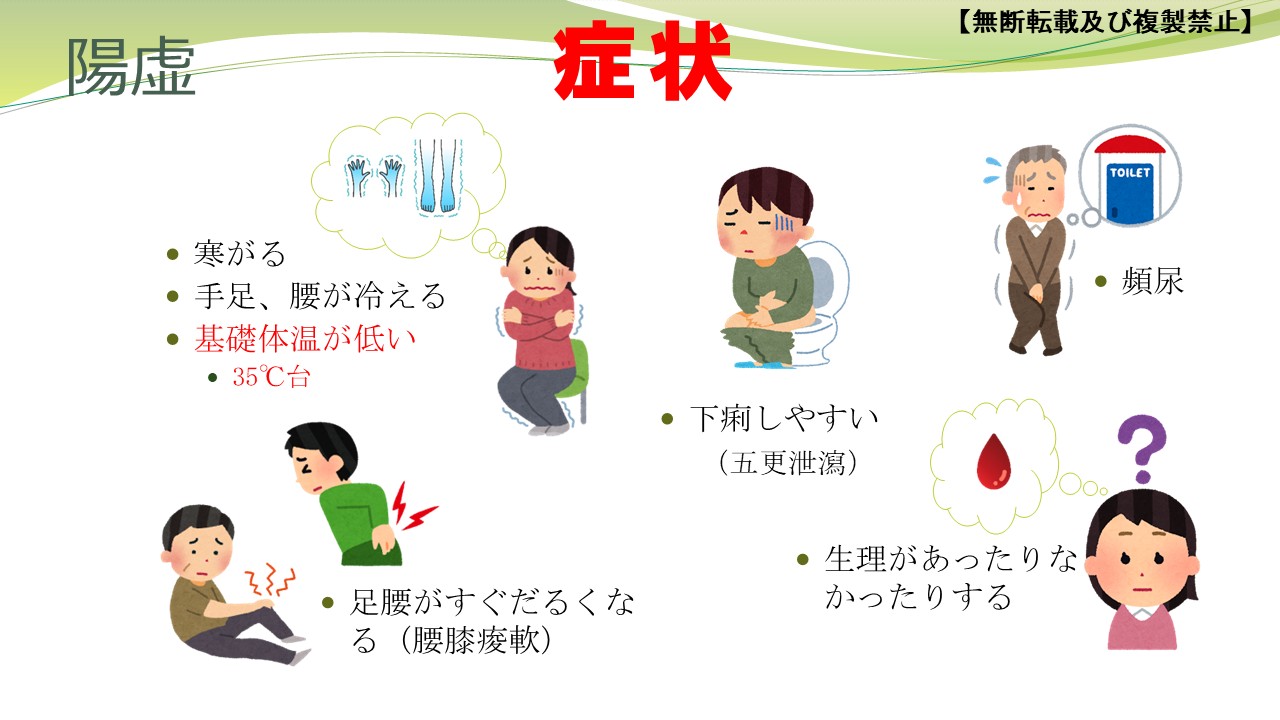『体質別養生法 第4回 ~陰虚~』
今回は、体質別養生紹介の4回目です。
とり挙げる体質は、『陰虚(いんきょ)』です。
陰虚は、簡単にいうと体の潤い不足です。
栄養を含む、血・水が不足しますので、ドライ(乾燥)症状や熱を伴う症状が起こりやすくなります。
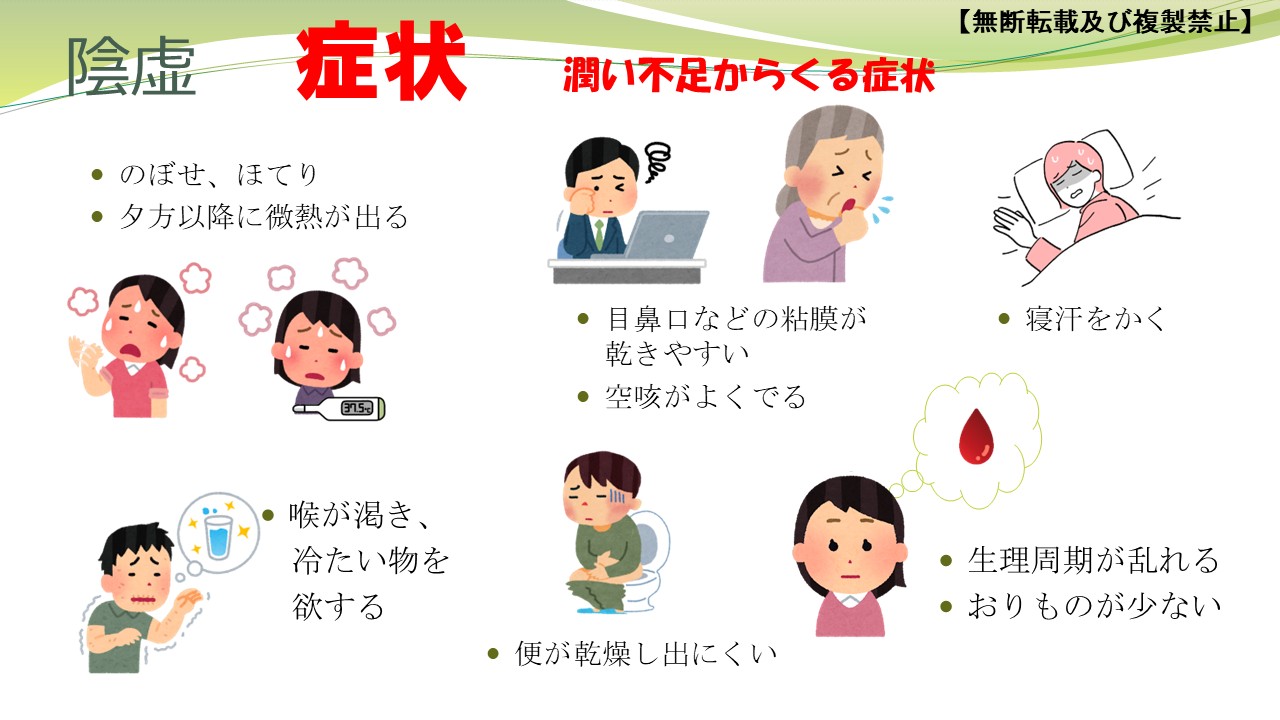
🔹のぼせ、ほてり
🔹夕方以降に微熱が出る
🔹目鼻口などの粘膜が乾きやすい
🔹空咳がよくでる
🔹寝汗をかく
🔹喉が渇き、冷たい物を欲する
🔹便が乾燥し出にくい
🔹生理周期が乱れる
🔹おりものが少ない
<養生>
回復の基本は日頃の養生です。陽虚同様、回復にはかなり時間を要します。(経験則ですが、回復期間は、半年から年の単位)
🔶十分な睡眠をとる(陰虚は、夜型生活の方に多い)
🔶適度な運動(大量発汗する程の運動は避ける)
🔶辛味(香辛料など)を控える
🔶過度な飲酒とタバコを控える
🔶冷たい飲食物を控える
🔶オススメ食材
れんこん、トマト、豚肉、豆乳、黒ごま、白ごま、ゆり根
貝類(あさり、しじみ、はまぐり、アワビ)、
豆腐、白菜、きゅうり、梨、りんご、レモン、スイカ
※陰虚は、消化力能力が低下している方が多いです。消化に優しい調理で摂りましょう。食べる量も腹八分目にしましょう。
次に陰虚体質で使う漢方薬の一例をご紹介します。
<漢方薬>
上述で、陰虚は潤い不足からドライ症状と熱症状がでます。よって、潤したり、熱をとったりする漢方薬を使っていきます。
◆のぼせ、ほてり
瀉火補腎丸(しゃかほじんがん)
知柏地黄丸(ちばくじおうがん)
杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)
亀板製剤(きばんせいざい)
六味丸(ろくみがん)
◆寝汗をかく
衛益顆粒(えいえきかりゅう)
麦味参顆粒(ばくみさんかりゅう)
◆目鼻口など年開くが乾きやすい
杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)
八仙丸(はっせんがん)
滋腎明目湯(じじんめいもくとう)
石決明製剤(せきけつめいせいざい)
◆生理不順
婦宝当帰膠(ふほうとうきこう)
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん)
◆乾燥からくる便秘
麻子仁丸(ましにんがん)
陰虚の回復は、養生と漢方の継続が重要です。あせらず、続けて回復を目指しましょう
上述の漢方薬は一例です。他にも色々ありますので、ご相談ください(^^b
<注意>
本ページで掲載している漢方薬は一例です。
個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。
漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。
熊本 菊陽町 菜の花漢方堂